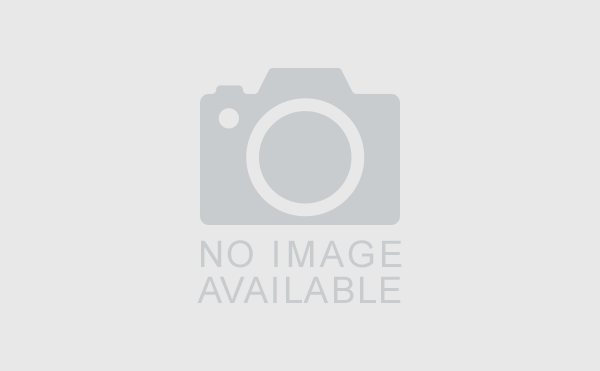ISO9001_オンライン情報交流会(内部監査編)随時開催
弊社では、ISO9001_オンライン(内部監査編)情報交流会を企画しています。
参加希望者のご要望で、随時開催いたします。
案内は、最後尾に記載。
まずは、こちらをご参照ください。
☆情報交流会のひとこまです。
(略)
A社:内部監査員の認定を、外部公開研修を条件にしていますが、その後の教育を、どのようにすれば良いか思案しています?
本多:そうですね、外部監査の機会に触れることは、ひとつの学習の機会になると思います。審査機関の定期審査、更新審査や、他にも、顧客の審査や供給者への審査も、外部監査における接点といった意味からは、良き機会ですね。
ただ、内部監査に関して問題意識をもって臨めばとの前提ではあります。内部監査は、第3者監査とも、第2者監査とも異なり、自社のQMSを如何に有効にしていくか?そのネタを抽出することにあると思いますので、そのためにどんな工夫をしたらよいのか?組織で常に問題意識を持っていれば、いろいろと内部監査を改善していくヒントは見つかってくるものと考えます。
それに、今回のような、他社との情報交流会の場は貴重な機会に違いありません。
B社:弊社では、毎回毎回、同じような監査で、やる意味に疑問を持ったり、ただ、儀式的に済ませたりしている感がありますが、何か工夫をしている例はありますか?
C社:当社では、年度目標への取り組みや発生したトラブルへ対応の取り組みを重点課題に挙げて、監査を実施しています。毎回マンネリといった感じはありませんね。
本多:良い取り組みですね。まず内部監査の要求事項で確認しておきたいこととして、内部監査で診ることは大きくふたつです。適合と有効性。認証取得をして長年経過した組織は、特に有効性に焦点を当てた監査を志向していきたいものです。
B社:なるほど。
本多:年度目標への取り組みについては、私も、こだわりをもって観察します。やはりISOマネジメントシステムは、アウトプット志向・パフォーマンス重視でなければいけません。目標に関しては、目標の設定や、現場での目標の認識、取組内容の計画と進捗。これらを、何よりも、現場の第1線の方々に対して、確認します。すなわち、「あなたに関係する目標は何ですか?」、「目標に対して実績推移はどうですか?」、「昨日の目標に対する実績はどうですか?」、「これまで、取り組んだことは何ですか?成果はどうですか?」、「今取組べきことは何ですか?」などを尋ね、かつその事実を3現主義で確認します。要求事項でいうと、“認識”。私が、ISO9001要求事項の中で、最も重きをおく要求です。
C社:当社では、なかなかハードル高い感じがします。
本多:確かに。あまり突っ込むばかりでもいけないので、そこら辺は、組織の成熟度に応じて、詳細度や接し方を変えたりしています。
発生したトラブルの処置やその後の対応に対しても、重視しているポイントです。その場限りの話にとどまらず、その内容が、その時、会議などで共有することは、もちろんのこと、引き続き、時間が経過しても、新たな人が関わっても、その対策が実行できるように落とし込まれる仕組みになっているか? 3現主義で確認します。要求事項でいうと“組織の知識”となり得ているか?っですね。
B社:ウーン。“組織の知識”って要求事項、それほど深く意識していないかも。
本多:“組織の知識”は、2015年版で新たに加わった要求です。“組織の知識”ですから、時間が経過しても、新たなひとが関わってもにはこだわってほしいですね。
そういえば、内部監査要求事項で、2015年版に新たに加えられた内容があります。何でしょうか?
各社:、、、、、さて、何でしょう??
本多:「組織に影響を与える変更を内部監査プログラムに考慮する」。この内容、品質マニュアルには記載してある。また、潜在的には実施している組織もありますが、意外に、こんな要求あるんだ?って改めて確認される組織も少なくありません。
C社:当社では、最近大きな組織変更ありましたが、こんなことが該当するんでしょうかね?
A社:うちでも、何かしら変化点があったら、問題なく運用されているか診ているようなことが多いと思いますが、意識して必ずってまではいけてないと思います。
B社:今聞いたようなことを、監査で押さえるようにするのは、どうするんでしょう?
A社:当社では、計画、チェックリスト、報告書様式に、こんなのを使用して、意識されるようにしています。監査前の重点監査事項の共有や監査後の各内部監査員の指摘に対する組織としての方向性を検討する場を持ったりもしています。
各社:うちは、、、、、、、。こんな感じですね。
本多:各社いろいろと参考になりますね。私もよく参考にしてもらうこんな帳票例があります。
今お話しした点や、他にも、箇条順番通り/一問一答的な形式的監査にならないよう、チェックリストでは、未熟練者にとって監査する順番に示唆を与たりしています。
各社:〇社のこんな点は、当社も取り入れてみようかと、、、
A社:当社も長くISO取り組んでいますが、いまひとつ根付いていないといううか。何か他社では、どうやっている?とかあれば教えてください。
B社:xxxx
C社:xxxx
本多:逆にひとつ質問ですが、ISOに取り組んでいなければ、今やっていない内容には、何がありますか?
A社:内部監査。それに、目標設定及びその取り組みも、毎年はやっていないかもしれません。
本多:だとすると、ISOをやって良かったと言えるように思えますが、、。内部監査は、とても良い仕組みと思っています。中々、自社とは言え、他部門の仕事のやり方は分かっていないといった組織は多いでしょう。それを知る機会としても、意味があると思います。年度目標の設定や取り組みも是非とも、積極的に取り組みたい内容です。
他には、どうですか?
A社:文書管理はやっかいかも。
本多:そうですか。もしも文書管理がやっかいというのなら、何か改善の必要性が潜んでいるものと推察します。一度見直してほしいものですね。
今言われたような、やっかい!や根付いていないと思われるような内容も、なんとなくではなく、顕在化したいものです。内部監査の機会に、これらを情報交換の中で顕在化させていくのも、内部監査の有効な活用に思います。
B社:計測機器管理にお金がかかるが、今やっている対象機器は適切か?顧客満足にアンケート方式をとっているが、正しい情報が検出できているのか?毎年行っている購買先の評価も現実的な方法を模索しては? などに疑問を持っているかもしれません。
A社:内部監査を、こんな問題意識をもっての情報交換の場にすると良いかもしれません。
B社:こんなのもありですよね。
(つづく、略)
こんな感じで、参加者の日頃のお悩みことを起点に、参加企業の事例情報交換や意見交換をしてもらっています。
お悩みごとからの話題に対して、例えば、下記のような問題意識をもっています。これら情報提供もしつつ自由な雰囲気で対話を進めます。
【内部監査の勘処考察】
・規格構造を念頭に
・上位指示展開
・監査全体を見据えて
・戦略的監査員割り当て
・双方向情報交流
・現地/実績ベース
・サンプリングが肝(意図、多角度)
・道標的チェックリスト
・ポジティブ所見/成長の軌跡フィードバック
【内部監査における診処考察】
・PDCAの短サイクル化と当事者意識
・報連相仕組みと文化
・品質ヒヤリ含む情報共有と組織の知識化
・決める/守る/直す/守る
・”初めて、変更、久しぶり”(3H)の管理
・異常(止める、品質確認・復帰)対応と再発対策
・現場リーダーマネジメント力量
・デジタル活用
☆あらためまして、本企画のねらい
ISO9001の意図する結果は、要求事項に適合した製品を提供し、顧客満足を向上させることにあります。とはいえ、「品質追及というよりも、ISO認証維持活動にはなっていないだろうか?」「もっと品質に直結した効果的な仕組にできないか?」、「もう少し簡潔にならないか?」こんな疑問や懸念をもっていながらも、さて、どうすれば良いか??見いだせずに、そのままの運用をしている企業様に。
また、しばらく慣れ親しんだQMSに疑問を感じずに運用するようになってきたが、「鈍感になってきてやしないか?」こんな危機感を抱く企業様に。
「他社では、どうやっているんだろう?」。
自社の仕組しか知らない組織にとっては、他社の仕組に触れることは、良き機会になることでしょう。
今回は特に、内部監査のやり方に関して、他社との意見・事例交換を通じて、疑念や疑問解決へのヒントを探っていただきます。
**情報交流をしたい企業様
何社か(3社程度)集いましたら、随時オンラインで行いたいと思います。
(想定:2時間程度~MAX3時間、(1万円+消費税)/社 2名まで/社 @参加企業数や要望等により調整) 連絡先:info@kaizen-wp.jp
☆本多:JRCA登録QMSエキスパート審査員、主任審査員、管理技術者
全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(品質保証、プロダクション)